続きです。
適性Ⅰの分析で、適性対策をしっかりしていないと解けなかったのが大問2の問題2です。
問題の情報量がかなり多いのですが、最後の条件をきちんと当てはめると解答が1パターンになる問題でした。
これは相当時間かかった人多いんじゃないかなと思います。
条件が最後の最後に書いてあったので、適性対策していなかった生徒(適性対策してた生徒でも?)はそれを読み飛ばして答えを出してしまったのではないかなと。
完答でしたしね。
また、適性らしい資料読み取りは大問4の問題3です。
ただ、昨日のブログにも書いた通り資料読み取りだけなので、そんなに難しくはないかなと思います。
考察までさせてませんし。
そして、中学受験らしい問題かなと思うのが大問1の問題2、大問2の問題2の水の量、大問4の問題2です。
これらの問題はすべて時間をかければ解けるのですが、中受の知識があった方が圧倒的に早く解けたと思います。
大問1の問題2は中受の算数をやってた生徒は多分1~2分もかからないでしょう。
算数分野は「図形」「規則性」「場合の数(行動計画)」の出題なので特に分野に大きな変化はありませんでした。
行動計画は後期の授業でも冬期講習中でも問題やらせてましたし、規則性なんてどんだけやったんだってぐらいやってましたから
ぜひともできててほしいと思っていたところ8~9割台がいたので、ちゃんと出来ててホッとしました。
平均点は去年より下がるのかなと思いますが、適性Ⅱの出来によりますけど上位の学校であれば適性Ⅰは6割は届いてほしい問題です。
中堅校であれば4割ぐらいでしょうか。
先ほど述べた通り適性Ⅱがどれくらいできたか次第です。

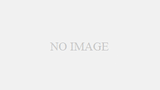
コメント